コラム
社会が近代化・産業化するという歴史的な変化ののちに、私たちの社会では自然に他者と経験を共有し、理解することが難しくなっていると考えられます。それゆえ、子育てに関しても、社会の側が環境を整えるとともに、周囲の人が想像し、理解し、サポートできる社会を実現する必要があると思っています。私たち研究班も、今だ未完の取り組みですが、周囲の人が「生誕1000日見守り隊」として、必要なときにそっと手を差し伸べられる社会を皆さんとともに作っていくことができればと考えています。
*写真はイベントなどで配布している「生誕1000日見守り隊バッジ」です。
*写真はイベントなどで配布している「生誕1000日見守り隊バッジ」です。

中本 剛二
専門:文化人類学
大阪樟蔭女子大学准教授
大阪大学特任准教授
#002
2025.07.30
未完のプロジェクト・「生誕1000日見守り隊」にむけて
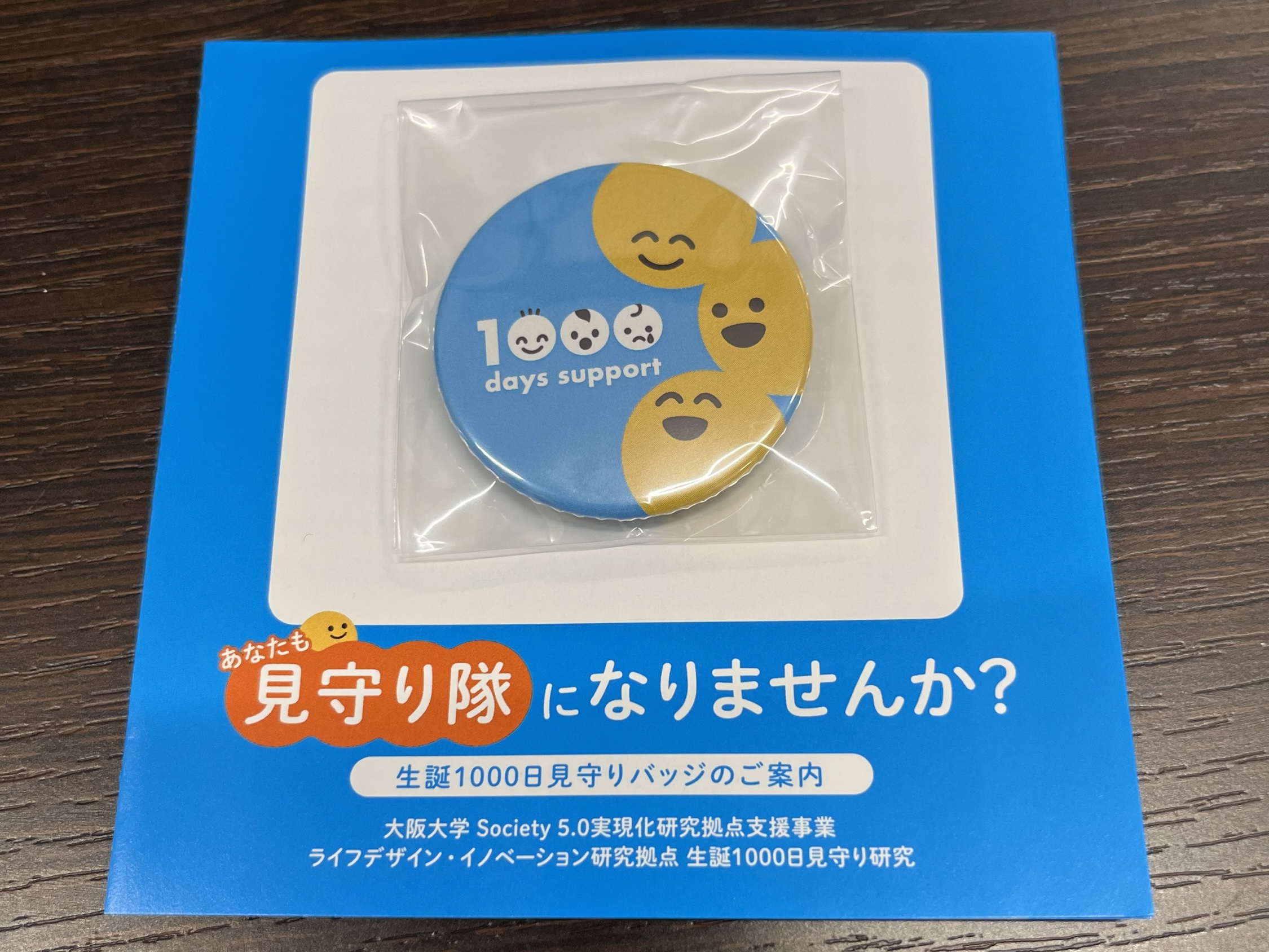
私たち研究班の第1の目標は、「子育てしやすい社会を作る」ことです。それは現在、多くの子育て中のお母さん、お父さんが、孤立している、不安を抱えているという認識に基づいています。私たちが今、社会を営み生活をしていることを考えると、現生人類の(すこしおおげさですが)約30万年ともいわれる長い歴史の中で、出産し、子育てすることはライフサイクル上必須のイベントであったと考えられます。それがなぜ、今日では大変なことになってしまったのでしょうか。
その理由を、一言で簡単に表すのは難しいですが、思いつくものの一つとして、社会が近代化・産業化する過程で、共同体の在り方や、人と人とのつながり方が変質してしまったからではないか、というのがあります。その変質の内容については、多くの学術的な議論があり、詳しく説明する余裕はないのですが、おおむね、似た者同士が作る共同体で、地縁や血縁でつながり相互に扶助する(一方で、抑圧も厳しい)関係性から、専門分化し、利害や合理性に基づく関係性(それゆえ、プライバシーには立ち入らない)に変化したという内容が含まれていると思います。
特に日本では、高度成長期を経て大きく社会が変容したと言われます。どちらのありかたがいいと一概に言えることではないのですが、後者の社会の色合いが強くなればなるほど、ほかの人の人生や生活の全体像を、直接的な経験で知ることは難しくなると考えられます。子育てに関しても、かつては周りで自然に行われていて習得できていたものが、後者では見たり学んだりする機会も、大きく減じたと考えられます。そしてほかの人と個人的な関係性を創ったり、助け合ったりできるかどうかが、共同体によって準備されたものではなく、個人の置かれた環境やその人のパーソナリティにゆだねられることになります。
このような現状に関連して、インタビューの中で、子育て中という状況を、以下のようにとてもうまく表現してくれたお母さんがいました。
「最近、小さい子どもがいるっていうのがどういう感覚かってわかってもらいにくい、理解されにくいなと思っていて。たとえば普段使っている最寄り駅とかで、海外出張とかに行くときに大きな荷物を持ってガラガラっと引くと、初めてバリアフリーじゃないことに気付くことがあるじゃないですか。自分の家から空港まで、実はものすごく困難な道のりだと。同じようにベビーカーもそうですけど、普段はスタスタ歩いてるけれど、ちょっと何かハンディキャップ的なものがあると急にものすごく生きづらさを感じるようなことが、そういうかばんとかだととてもわかりやすい例かなと思うんですけど、それが子ども、子育てにあることに初めて気付いて。」※
この方は、ご自身が子育てするに至って初めて、子育てがどういうものか実感したといいます。それは子育て中の当事者がいわゆるマイノリティになってしまうということです。具体的な体験としては休みの日にどうしても出勤しなければならないとなった時にも、子供を預かってくれるところがないことや、小さい子供がいても夫に対しては、職場で考慮されないこと(いわゆる勤務時間外にも予定がどんどん入ってくること)などを話されていました。
これらのことを考えると、子育て中の状況はそのほかの人からからとても見えにくくなっていること、そして子育ての当事者(お母さん・お父さん、ご家族)の自助努力には限界があることを強く感じます。それゆえ、当事者を取り巻く環境について、周囲の人が想像し、理解し、サポートしようとする姿勢が強く望まれることを感じます。あえてもっと言うならば、お母さん、お父さん、ご家族だけを当事者とするのではなく、周囲の人が当事者として一緒に考えることが必要なのだと思います。
私たち研究班は、子育ての環境に関して、Society5.0の技術を用いて、子育ての経験と知識が循環する社会を目指しています。この取り組みについてはこのホームページをはじめとする様々な場で説明をしていますので、そちらをご覧ください。そして、いまだ未完の取り組みとして、周囲の人が子育てについて考え、見守り、そして必要な時にはそっと手を差し伸べられる社会の在り方についても考えてきました。そしてそれらの取り組みを「生誕1000日見守り隊」として、実現したいと思ってきました。私たちが各種のイベントなどに参加するときには、その思いを記したリーフレットと、バッジを配布しています。
そのような「生誕1000日見守り隊」は、今だ具体的な形を結んでいるわけではないですが、私たち研究班のメンバーはいつかそのような社会の在り方を、皆さんとともに経験できることを夢見ています。
※読みやすさを考えて、語尾等をすこし整えています。
中本剛二(文化人類学・民俗学)
その理由を、一言で簡単に表すのは難しいですが、思いつくものの一つとして、社会が近代化・産業化する過程で、共同体の在り方や、人と人とのつながり方が変質してしまったからではないか、というのがあります。その変質の内容については、多くの学術的な議論があり、詳しく説明する余裕はないのですが、おおむね、似た者同士が作る共同体で、地縁や血縁でつながり相互に扶助する(一方で、抑圧も厳しい)関係性から、専門分化し、利害や合理性に基づく関係性(それゆえ、プライバシーには立ち入らない)に変化したという内容が含まれていると思います。
特に日本では、高度成長期を経て大きく社会が変容したと言われます。どちらのありかたがいいと一概に言えることではないのですが、後者の社会の色合いが強くなればなるほど、ほかの人の人生や生活の全体像を、直接的な経験で知ることは難しくなると考えられます。子育てに関しても、かつては周りで自然に行われていて習得できていたものが、後者では見たり学んだりする機会も、大きく減じたと考えられます。そしてほかの人と個人的な関係性を創ったり、助け合ったりできるかどうかが、共同体によって準備されたものではなく、個人の置かれた環境やその人のパーソナリティにゆだねられることになります。
このような現状に関連して、インタビューの中で、子育て中という状況を、以下のようにとてもうまく表現してくれたお母さんがいました。
「最近、小さい子どもがいるっていうのがどういう感覚かってわかってもらいにくい、理解されにくいなと思っていて。たとえば普段使っている最寄り駅とかで、海外出張とかに行くときに大きな荷物を持ってガラガラっと引くと、初めてバリアフリーじゃないことに気付くことがあるじゃないですか。自分の家から空港まで、実はものすごく困難な道のりだと。同じようにベビーカーもそうですけど、普段はスタスタ歩いてるけれど、ちょっと何かハンディキャップ的なものがあると急にものすごく生きづらさを感じるようなことが、そういうかばんとかだととてもわかりやすい例かなと思うんですけど、それが子ども、子育てにあることに初めて気付いて。」※
この方は、ご自身が子育てするに至って初めて、子育てがどういうものか実感したといいます。それは子育て中の当事者がいわゆるマイノリティになってしまうということです。具体的な体験としては休みの日にどうしても出勤しなければならないとなった時にも、子供を預かってくれるところがないことや、小さい子供がいても夫に対しては、職場で考慮されないこと(いわゆる勤務時間外にも予定がどんどん入ってくること)などを話されていました。
これらのことを考えると、子育て中の状況はそのほかの人からからとても見えにくくなっていること、そして子育ての当事者(お母さん・お父さん、ご家族)の自助努力には限界があることを強く感じます。それゆえ、当事者を取り巻く環境について、周囲の人が想像し、理解し、サポートしようとする姿勢が強く望まれることを感じます。あえてもっと言うならば、お母さん、お父さん、ご家族だけを当事者とするのではなく、周囲の人が当事者として一緒に考えることが必要なのだと思います。
私たち研究班は、子育ての環境に関して、Society5.0の技術を用いて、子育ての経験と知識が循環する社会を目指しています。この取り組みについてはこのホームページをはじめとする様々な場で説明をしていますので、そちらをご覧ください。そして、いまだ未完の取り組みとして、周囲の人が子育てについて考え、見守り、そして必要な時にはそっと手を差し伸べられる社会の在り方についても考えてきました。そしてそれらの取り組みを「生誕1000日見守り隊」として、実現したいと思ってきました。私たちが各種のイベントなどに参加するときには、その思いを記したリーフレットと、バッジを配布しています。
そのような「生誕1000日見守り隊」は、今だ具体的な形を結んでいるわけではないですが、私たち研究班のメンバーはいつかそのような社会の在り方を、皆さんとともに経験できることを夢見ています。
※読みやすさを考えて、語尾等をすこし整えています。
中本剛二(文化人類学・民俗学)


